こんにちは!『The Crafty Garden Lab』の管理人Kouです!
今回のテーマは『我が家の烏骨鶏』です
烏骨鶏の特徴
烏骨鶏は、『烏(カラス)』のようの黒色の『骨』と体(皮や肉)を持った『鶏』です。羽毛は種類によって白や黒、茶といった色がありますが、体と骨は決まって黒色です。
烏骨鶏は、たくさんある鶏の種類の中でも野生の特性を強く持つ鶏です。そのため繁殖期が明確になっています。産卵して、抱卵して、子育てをする。そのサイクルが明確になっているため、烏骨鶏の産卵数はかなり少ないですが、ヒヨコを孵して育てることはお手の物です。
烏骨鶏は、一般的な鶏と比べて指の本数が多いです。一般的な鶏は足の指が4本ですが、烏骨鶏は5本あります。
烏骨鶏は、雄と雌の判別がつきにくいことがあります。一般的な鶏の雄は立派な赤い肉冠を持ち、雌は赤い肉冠が小さいことで見分けが付きます。しかし、烏骨鶏は赤い肉冠を持たず黒紫の潰れた肉冠か羽冠(羽毛の冠)を持ちます。さらに雄も雌も肉冠か羽冠を持つためパッと見では見分けがつきません。成鶏となった時に、『鳴き声』や『体格差(雄は大きい)』で判断するしかありません。羽冠の形でもわかるようですが、見慣れないと難しいみたいです。(羽冠が後ろに流れていると雄、上に盛り上がってフワッとなっていると雌です。)
烏骨鶏の産卵数
烏骨鶏の産卵数はかなり少ないです。みなさんが口にする鶏卵はスーパーなどで購入することがほとんどだと思います。スーパーなどで売っている鶏卵は産卵用に品種改良された鶏が産んでいます。産卵用の鶏の年間産卵数は約350個ほどで、ほぼ毎日産みます。しかし、烏骨鶏の年間産卵数は約50個程度です。烏骨鶏にも産卵数を増やすように品種改良されたものもいます。品種改良された烏骨鶏でさえ150個ほどしか産まないとされています。
そんな烏骨鶏の卵は、一般的な鶏の卵と比べて栄養価が高くて貴重なため、1個あたり100円以上します。
烏骨鶏の子育てサイクル
烏骨鶏は、野生の特性を持つ鶏のため、『産卵期』、『抱卵期』、『子育て期』があります。
『産卵期』に卵を産みますが、その期間は約2週間で10個程の卵を産みます。
『抱卵期』に卵を温めます。鶏の卵は21日間温めると孵化します。烏骨鶏の抱卵期は21日プラス数日の約30日間です。抱卵期に抱卵する卵がない場合は抱卵期は短くなり、抱卵していても卵が孵らないと抱卵期が長くなる傾向があります。
『子育て期』はヒナを保温したり子育てをします。孵化したヒナは体温調節がうまくできないため、母鶏の羽毛の中に入って温まります。少しずつ母鶏の羽毛の外に出て外の世界に慣れていきます。外気温に慣れるまで1カ月程かかります。その後も2ヶ月程は母鶏から離れようとせずいつも母鶏にくっついて行動します。合計で3ヶ月くらいはヒナは母鶏と一緒にいます。この期間を子育て期と言います。
『抱卵期』と『子育て期』を合計した約4ヶ月間は卵を産まなくなります。子育て期がなくても抱卵期が終わってからしばらくは母鶏が体調を戻す期間(回復期)があり、その期間は約2週間です。『産卵期』、『抱卵期』、『回復期』を合計すると約2ヶ月で、その期間で卵を約10個しか産まないため、烏骨鶏の産卵数は年間で約50個となります。
飼育環境


鶏の飼育面積は、平飼いで1坪当たり10羽以下が望ましいとされています。1坪は3.3㎡なので1羽当たり0.33㎡となります。わたしが烏骨鶏を飼っている小屋は、1.6×3.4mで5.44㎡となるため、5.44÷0.33で16.4羽までなら許容されます。窮屈な環境では鶏にストレスがかかってしまい、卵を産まなくなるどころか、喧嘩して怪我したり病気になったりするなど問題が起こります。わたしの鶏小屋の隣には、小屋と同じくらいの広さの屋外に柵とネットで囲ってあるスペースがあり、できる限りそこで自由に遊べるようにさせています。また、鶏は群れで生活するため1羽当たりで飼育面積を計算するより、1坪当たりで計算したほうが良いです。
飼育面積以外にも、通気性や暑熱対策、寒冷対策を施す必要があります。人間と同じで住みやすい環境を整えることが重要です。しかし、一度に全てに対応できるような環境を作るのは難しいので、少しずつ、飼育小屋に合わせた工夫をしていくといいと思います。
烏骨鶏のご飯
烏骨鶏を含む鶏は雑食です。なんでも食べると言っていいくらいです。しかし、中には消化不良を起こしたり病気の原因になるものもあるので注意が必要です。例としてわたしが烏骨鶏にあげているものを記します。
- 市販のエサ
- とうもろこし
うちで栽培したけど食べれそうにないもの。 - スイカ
うちで栽培したけど食べれそうにないもの。 - サワガニ
うちに流れている沢にいるやつ。 - みみず
畑とかにいるやつ。 - カナブンなどの幼虫
畑とかにいるやつ。 - 雑草
そのあたりに生えているやつ。 - キャベツ
- にんじん
- きゅうり
- トマト
食べさせてはいけないものとしては、ほうれん草やネギ類は消化不良を起こすため与えてはいけません。上に挙げたわたしが烏骨鶏にあげているものの中にも寄生虫がいる可能性があるものがあるため、烏骨鶏や鶏にあげる場合は自己責任でお願いします。
懐きやすさ
烏骨鶏は、とても人懐っこい鶏であると思います。ヒナのうちからたくさん接してあげると、足音を聞き分けて走り寄ってきます。わたしはご飯をあげるときにペットボトルにエサを入れてカシャカシャ音を立てるようにしていますが、それを続けているとカシャカシャ音がするとエサがもらえるとわかって走り寄ってきます。
懐きやすい反面、懐かせようとしないととても攻撃的になりやすいと感じます。特にメスが抱卵期や子育て期に入るとオスがメスを守ろうとして、メスに少し近寄っただけで足蹴りしてきます。
孵化から産卵まで
烏骨鶏は、孵化してから産卵できるようになるまでに約150日かかります。ほかのサイトでは210日かかると記載されているところもあります。孵化してからの環境が過ごしやすい環境だと産卵開始までの期間が短くなるようです。間を取って、孵化してから半年後を産卵開始の目安にするのがいいかもしれません。
今回はここまでになります。烏骨鶏は鶏なので烏骨鶏以外にもここで記載した内容は流用できると思います。しかし、今回の内容はわたしの経験をもとにしたものなので、文献とは違った解釈をしている内容があると思いますが、その点はご了承ください。
今後ともよろしくお願いしますm(_ _)m

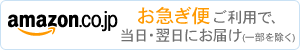

コメント