この記事は、AIのchatGPTに助言を受けながら、私自身の学びも含めて記事にまとめています。
ここでは、管理人Kouが英語を学習していく中で感じた素朴な疑問を、AIロボの『Tellu(テル)先生』と一緒に解決していきます!英語のよくある間違いや、使い方で迷う表現を一つずつ解説していくので、ぜひ私と一緒に楽しく学びながらステップアップしていきましょう!
“go for ”の使い方

Tellu先生!この前、パートナーにお米を買って来てほしいと頼まれました。
『どのくらいの値段なら買ったほうがいい?』って英語で言うとき、何て表現したらいいですか?

こんにちは、Kouさん!いい質問ですね!シチュエーションによって、いくつかの言い方があります。
たとえば、どのくらいの価格帯のものを選べばいいか聞きたい場合は、
“What price range should I go for?”
もしくは、
“How much should I spend on it?”
こう言うのが自然な表現です。
カジュアルな場面なら“How much should I spend?”が使いやすい表現です。

そうなんですね!
“go for”は、どんな表現になりますか?

“go for”は、状況によってさまざまな意味になりますが、基本的に 「選ぶ」「狙う」「目指す」「求める」 というニュアンスを持ちます。
以下が詳しい説明になります!
- ~を選ぶ、~にする
- I think I’ll go for the salad.(サラダにしようかな。)
- Which one should I go for?(どっちを選べばいい?)
- ~を目指す、~に挑戦する
- I’m going for the gold medal.(金メダルを目指している。)
- She decided to go for the promotion.(彼女は昇進を目指すことに決めた。)
- ~に向かう、~を狙う
- Go for the best deal.(一番お得なものを狙いなよ。)
- Go for the cheapest option.(一番安い選択肢を選んで。)
- 「どのくらいの値段なら買えばいい?」の場合
- What price range should I go for?(どのくらいの価格帯を選べばいい?)
→ 「どのくらいの価格帯のものを狙えばいい?」というニュアンスになります。
- What price range should I go for?(どのくらいの価格帯を選べばいい?)
“go for”はカジュアルな表現なので、日常会話でよく使われます。

なるほど!
では、よく耳にする“go for it ”は、『それを選んだら良いよ』ってニュアンスでしょうか?

“Go for it!”は、「それを選んだらいいよ」ではなく、「思い切ってやってみなよ!」という応援のニュアンスなので、もし「それを選んだらいいよ」と言いたいなら、次のような表現の方が適切です。
“You should go for that one.”(それを選んだほうがいいよ。)
“I think you should go for this option.”(この選択肢がいいと思うよ。)
“Go with this one.”(こっちにしたら?)
“Go for it!”は、挑戦を後押しするフレーズ なので、「選ぶ」というより 「自信を持って決断することを勧める」 というイメージですね!

ということは、“go for”は、『完全に迷っている』というよりも、『(迷っていながらも)何にするかある程度決心がついている』状態でしょうか?

はい、その通りです!
“go for” には 「完全に迷っている」状態ではなく、「ある程度決心がついているけれど、あと一押しが欲しい」 というニュアンスがあります。
以下で詳しい説明をします。
- 完全に迷っている → 「どれにするか決められない」状態
- What should I choose?(どれを選べばいいかな?)
- I have no idea what to do.(どうすればいいか全くわからない。)
- ある程度決心がついている → 「どちらかに気持ちが傾いている」状態
- I’m thinking about buying this one.(これを買おうか考えてるんだけど。)
- Should I go for this one?(これにしようかな?)
→Yeah, go for it!(うん、それでいいよ!)
- もうほぼ決めている(背中を押してほしい)
- I’m going for the blue dress.(青いドレスにしようと思う。)
→Good choice!(いいね!)
- I’m going for the blue dress.(青いドレスにしようと思う。)
“go for”は、「完全に迷っている」というより、「気持ちがある程度固まっている状態」や「決断を後押しする」場面で使うのが自然です!

説明にあった、“be going for”は“go for”より決心が強い状態ということですか?“be going to”と“will”の関係に近い感じでしょうか?

そうですね!
“be going for”は“go for”よりも決心が強く、「もうほぼ決めている」状態を表します。これは“be going to”と“will”の違いと似ています。
“go for”のまとめ
- “go for” → まだ少し迷いがあるけれど、選ぼうとしている。
- “be going for” → すでに決めていて、実行するつもり。
- “be going for”は“be going to”と似たようなニュアンス で、「計画性がある決断」を示す。
- “go for”は“will”に近いニュアンス で、「その場での決断」に使われることが多い。
| 表現 | ニュアンス | 例文 |
| will | その場で決めた未来のこと | I think I’ll buy this book. (この本を買おうかな。) |
| be going to | すでに決めていた未来のこと | I’m going to buy this book. (この本を買うつもりだよ。) |
“spend”の使い方

よくわかりました!ありがとうございます。
“How much should i spend on it?”という例文がありましたけど、この文中にある“spend”は『留まる』って表現だったと思いましたが、それだと和訳がおかしくなってしまいます。

いい視点ですね!
“spend”は、「ある状態の中で時間を過ごす(費やす)」 という意味があり、ここから「費やす(お金を使う)」「過ごす(時間を使う)」という意味につながります。
以下で“spend”の基本の意味を説明します!
“spend”=何かを「費やす」「消費する」
お金 → 「お金を使う」
時間 → 「時間を費やす」
労力 → 「労力を使う」
- 「時間」の場合
“I spent the weekend at home.”(週末を家で過ごした。)
→ 「時間を家の中に留めた」 =「過ごした」 - 「お金」の場合
“I spent 5,000 yen on groceries.”(食料品に5,000円を使った。)
→ 「お金をそこに留めた」 =「費やした」 - つまり、“spend”=「あるもの(時間・お金など)を特定の場所や活動にとどめること」を意味する言葉で、「結果的に、そのものを消費・使用する」 という考え方になります。

なるほど!留まるって表現は副次的な表現で、主となるのは『使う』、『費やす』なんですね?
“pay”や“use”と“spend”の違いは、“spend”には『一定の物事に対して使い続ける』というニュアンスがあるところが違う。で合ってますか?

はい、その理解でバッチリです!
“spend”は、「あるもの(時間・お金・労力)を特定の目的のために費やす」 という意味が主になります。「留まる」というのは副次的な意味で、「特定の対象に使い続けて消費する」 というニュアンスが強いのがポイントですね!
以下で具体的な違いを説明します。
| 動詞 | ニュアンス | 例文 |
| spend | 時間・お金・労力を費やす(一定の対象に使い続ける) | I spent 5,000 yen on books.(本に5,000円使った。) |
| pay | 対価を支払う(お金を支払う動作そのもの) | I paid 5,000 yen for the book.(その本に5,000円支払った。) |
| use | 道具・リソースを利用する(使った後も残る可能性あり) | I used a credit card to pay.(支払いにクレジットカードを使った。) |
- spend(一定の対象に費やす)
- 「時間・お金を何かに注ぎ込む」 というニュアンス。
- 使うことが 継続的 だったり 量が重要 だったりする。
- ✅️I spent a lot of time studying.(勉強にたくさんの時間を費やした。)
✅️She spent all her money on travel.(彼女は旅行に全財産を使った。)
❌️I spent 5,000 yen for the book.(❌️spendは「目的」にonを使う)
→ ✅️I spent 5,000 yen on the book.
- pay(対価を支払う動作)
- お金の支払いそのものを指す。
- 金額 + for + 物 の形で使われることが多い。
- ✅️I paid 5,000 yen for the book.(その本に5,000円を支払った。)
✅️You need to pay for your drinks.(飲み物の代金を払わないといけないよ。)
❌️I spent 5,000 yen for the book.(❌ spendはforを使わない)
→ ✅ I spent 5,000 yen on the book.
- use(道具やリソースを利用する)
- 使っても消費しないこともある(繰り返し使えるものに使うことが多い)。
- 「使う」行為そのものを強調する。
- ✅ I used my laptop to write an article.(記事を書くのにノートパソコンを使った。)
✅ She used a coupon to get a discount.(彼女はクーポンを使って割引を受けた。)
❌️I used 5,000 yen on books.(❌ 本にお金を費やすならspend)
→ ✅ I spent 5,000 yen on books.

“spend”“pay”“use”の違いがよくわかりました!
話が戻りますが、お米に対して“spend on it”は、買い物はその時限りのことではなくて過去にもこれからも継続して行うことだから、“pay for”より“spend on”のほうが適切だという解釈であってますか?でも、“pay for”を使っても間違いではない。で合ってますか?

はい、その解釈はほぼ合っています!“spend on”と“pay for”の違いを考えるときに、「買い物の行為」 vs 「お金の流れ」 という視点で整理すると分かりやすいです。
“spend on” → 「お米にどのくらいお金をかけるべき?」(買い物をするたびに使う金額の目安)
“pay for” → 「このお米にいくら支払えばいい?」(目の前の特定のお米の価格)
今回の文脈では、買い物の継続性を考えると“spend on rice”がより適切ということですね!

なるほど!ということは、“spend on”は『わたしが行う行為』、“pay for”は『相手に行う行為』ってニュアンスでしょうか?

とても鋭い視点ですね!
“spend on”と“pay for”の違いを「わたしが vs. 相手に」という視点で考えると、確かにそのニュアンスが出てきます。
“spend on”は主語(= お金を使う人)に焦点があり、“pay for”はお金を受け取る側(= 売り手や支払う対象)にフォーカスがある。という違いになります。
“spend”のまとめ
- “spend”=何かを「費やす」「消費する」
- “spend on” → 私がどうお金を使ったかが重要(「わたしが」)
- “pay for” → 支払う対象や受け取る側が重要(「相手に」)
今回は少し長くなりました。最後までご覧くださり、ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いしますm(_ _)m

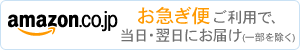

コメント